スペシャルインタビュー
ゲスト
第4回:村田英夫さん(民音北海道センター長・現民音常務理事)

第4回:村田英夫さん(民音北海道センター長・現民音常務理事)
第4回 村田英夫さん(民音北海道センター長・現民音常務理事)
聞き手:池田理事長・斉藤副理事長同席者:口中事務局長

挨拶 私達は一般財団法人民主音楽協会(民音)の教育支援事業の一環として、2005年から全国で172回の「親子のための手作り楽器体験学習会」というワークショップ(WS)を実施してきました。現在はコロナ禍で活動休止中なのですが、今回はその3分の1以上にあたる65回の開催を実施してくださった民音北海道センター長の村田英夫さん(現民音常務理事)にお話を伺います。
池田:今日はお時間頂き有り難うございます。村田さんに初めてお目にかかったのは2007年でしたね。
村田:そうです。当時北海道支部では別の団体に“親子のための手作り楽器体験学習会”をお願いしていたのです。作る楽器は本格的で演奏する音楽も素晴らしかったのですが親子が向き合って何かを作り上げると言う点で物足りなさを感じていたんです。そんな時に口中さんから池田さん達を紹介されました。
斉藤:私達の第一印象はどうでしたか?
村田:まず最初にマリンカンを紹介してくれたのですが、楽器そのものの事よりお二人が熱く語るその熱量に驚かされました。
口中:そうそう、私も初めてお二人にお会いした時に、お二人とも2時間以上、子ども達に伝えたい思いを熱く語って下さって圧倒されてしまいました。
村田:その情熱的な語り口調に接して“この人達とだったら面白いことが出来そうだな”と直感して、お二人にお願いすることを即決しました。
口中:そして2007年1月から北海道での WS がスタートしたんですね。実際の活動をご覧になって如何でしたか?
村田:池田さん達の WS は親子は勿論、私達スタッフまで一緒になって楽しかった。でも何よりも驚いたのは池田さん達の子どもに対する評価の仕方というか認め方でした。
口中:認め方ですか?
村田:そうです。どの子にも「イイネ!」と言えるところを見つけ出して褒める。お母さんが手を焼いているような、落ち着きのないお子さんや中途半端なやり方でいい加減な作業しかやろうとしないお子さんにまで、あんな認め方があるのか!と思うほど多角な観点で子ども達を認めて褒める姿に驚かされました。
池田:その点を見て下さっていたのは有り難いです。僕たちは常に子どもの中にある「その子らしさ・特性」を活かそうと考えています。そのためにはまずその子のありのままの姿を認めることから始める必要がある。そのベースにあるのが“音を楽しむ
ONGAKU”の大前提である“その人の感じ方が全て”という考え方なんです。
ある音を聴いた時に“良いな”と感じても“つまらない”“嫌い”“何も感じない”等、ど う感じても感じ方は人それぞれ自由!お互いにその感じ方を尊重し合わなければ、感じた
ことを素直に表現できなくなってしまう。自分の感じたことを素直に表現出来ることはと ても大切な事ですが、私達大人は社会性が身について、場の空気を読んで行動するために、時として正直な思いを素直に表現しない事も少なからずあるじゃないですか。。
斉藤:子ども達だって知らず知らずのうちに大人に認めてもらえるような発言をしていることがあるんですよ。だから“アッキー達はありのままの自分を表現しても
OK な存在だっていう安心感・信頼感”を子ども達にもってほしい。全てはそこからがスタートなんです。
村田:池田さん達が、会場内を元気良く?走り回ってしまうお子さんの足音をグループアンサン ブルの中に取り入れて“君はこのタイミングで走り回ってね!”と、作品の一部にしてしまったことがあった。持てあましていた会場を走り回る我が子のエネルギーを、プラスに 評価された時のお母さんの、ちょっと驚いたような嬉しそうな顔が今でも忘れられません。
池田:その点を見て下さったのも有り難いです。実は民音で WS を始めさせて頂く前、僕たちは 主に小学校の先生方対象の研究授業や WS の講師依頼を受けていました。でも民音の
WS は親子参加型。しかも年間通して何回も実施されたからこそ見えてきたものがあるんです。それが親御さんの、特にお母さんの子育てに向き合う姿だったのです。。
口中:と言うと?
池田:核家族化で相談出来る先輩がいない。少子化で子ども一人一人に対する周囲の期待も大きい。場合によっては自分でも忙しい仕事を持ちながらの子育てはお母さんにとって大きなプレッシャーになっていることがあるんです。当然笑顔になる余裕もありません。子ども達にとってお母さんが笑顔でいることが彼らの成長にとってとても大切な事なのに、それが難しい状況が多々あるっていうことが伝わってきたんです。
斉藤:そこで私たちは WS のターゲットを子ども達から親御さん、特にお母さん方の笑顔づくりのための児童理解や教育について、これまでの常識的な考え方から一歩離れた考え方を伝えることにシフトチェンジしたんです。だからそれまでは二人で子ども達の間を飛び回っていたんですけど、くにポンには親御さん担当としてジックリお話をしてもらうことにしたんです。
村田:なるほどそういうことだったんですか。ある時から池田さんの動きが以前ほど活発じゃなくなってきてたから、さすがのクニポンも年齢的に動けなくなってきたのかなと思ってましたよ(笑)。
池田:いやいやそんな風に見られていたなんてビックリ!僕たちはまだまだこれからも精力的に活動させてもらいますよ!
村田:それを聞いて私も一安心!今後ともよろしくお願いします!
斉藤:私達の方こそ、1日も早くコロナが収束することを願っています!
口中:今後とも私達の活動にご協力頂ければ有り難い限りです。今日は貴重なお時間を頂き本当に有難うございました!
第3回:作曲家・演奏家 野村誠さん
第3回「作曲家・演奏家 野村誠さん」野村さんは、1968年名古屋生まれの作曲家・演奏家。京都大学在学中に自身のバンドがCDデビュー。渡英し、各地でワークショップやコンサートを行いました。その後世界各地に招聘されるようになり、NHK「あいのて」の番組監修と出演が反響を呼びました。第1回アサヒビール芸術賞受賞。著書・共著は多数。

インタビュアー:横川雅之 同席者:池田理事長・斉藤副理事長
作曲家の道へは偶然?必然?
横川「どんなきっかけで作曲を始めたのでしょうか?」
野村「8歳の時に病気でずっと家にいて、ピアノのレッスンにも行けず娯楽もないので一人で作曲することが続きました。
友達と遊べていたら違う人生だったかも知れません。」
横川「でも、それで終わってしまう人もいますよね?」
野村「病後、ヤマハのグループレッスンに行ったんですが、自分 一人だけの日があって、先生が持っていたレコード(バルトークの曲)を聴いたんです。これがすごく面白くて、こんな音楽があるんだと思って。それで作曲家になろうと思いました。
バルトークの話や興味があるこ とを話してくれて、めちゃくちゃ面白かった!先生は全然何も教えなず、時間を潰してただけですけど…。事故のような出会いでした。尊敬する人がバルトークになり、すごい音楽を聴いた!あれやろう!と思いました。」
横川「音楽大学には行かなかったのはどうしてですか?」
野村「その先生の先生は戸島先生と言う作曲家で、僕は音大の作曲科に入りたかったので訪ねました。僕の作品を見ても曲についてはコメントしてもらえず、謎の言葉を言ったんです。
『これは作品というよりは君の演奏だね。』
もう1つは『作曲科の学生で先生に【ここ直せ】って言われたとこを直しているのは一流になれない。』、それで弟子にしてくださいとは言えなかった。
それで「あ、僕は一生習えないかも…弟子入りしてはいけないんだ」と思いました。
それは結構な衝撃で、どうしていいか道が全く無くなって、本当に戸惑いました。」
結局、野村さんは大学では数学科に入りました。自分で道を開かねばならず、コンサートに行って「この曲僕が書いたんですが…」と言ったり「ピアノが無いなら弾きに来ていいよ」と言われたり。下宿の六畳一間には楽器はありませんでした。
横川「頭だけで曲を書いたのでしょうか?」
野村「そうですね。ですから頭でっかちになっていました。大学には弾ける人がいないのに書いても意味が無いと思いました。
大学3年の時、ジョン・ケージが京都賞を取ったのでジョン・ケージの音楽を演奏するコンサートをやりました。
実際にバケツを叩くでも何でもやってみようと。実際に音を出す現場があるというのは、机上で作るのとは全く違うので、面白かった。」
集まってバケツを叩いたりするだけでも、それで音になって出来上がっていく。こうして野村さんは、もう少し現場で体を動かしながら音楽を作っていくことをした方がいいと思うようになりました。やがてイギリスに行くことになります。
イギリスへ、そして池田理事長との出会い
横川「イギリスではどんな体験をしたのですか?」
野村「小学校にアーティストが行っている様子をいっぱい見ましたが、うまくいっている部分やそうでない所を色々見て、日本の音楽教育の人にこれを伝えた方がいいんじゃないかなと思いました。
自分が体験したことはレアなことだなと思って。帰国してからその体験を書いたので、本を出したいと思って原稿を音楽之友社に問い合わせたんです。
急に本は出せないけど教育音楽という雑誌に連載しないかと言われて、連載を始めました。」
池田「なるほど!僕は既にその本に連載をしていて、隣のページが野村さんの連載だった。」
横川「ここで野村さんと池田さんが繋がったわけですね!実際の出会いは?」
野村「連載とは別に、鍵盤ハーモニカの特集記事を書いて欲しいと言われましたが、『鍵盤ハーモニカについては書けますが子どもとどういう活動ができるのかについては分からない』と言ったら、すごくいい先生がいるので会わせたいと言われて、池田さんと会うことになりました。」
池田「初めて会ったときの事を覚えてますよ!変な兄ちゃんが来たなぁと…」
野村「池田さんの連合音楽会のCDをもらって聴きました。これ面白いなぁと思いました。
知り合いの音楽家にも聴かせて、『これ面白いね!この音何の音?この人に会いたいね。』などと言い合って。」
数年のブランクの後、2000年頃に名古屋のイベントに池田さんを呼びました。その後海外のイベントにも池田さんを度々招待して2人の交流が続いていきました。
曲を演奏する、聴く…そこには人が介在する。
野村「作曲家が譜面を書くところまでは、人は全く介在していません。
でも演奏するのは人で、聴くのも人で、どういう風に演奏するかで全然違ってしまいます。
物理的な音響現象をどのように捉えて音楽をつくるかということと、人がどんな風に演奏するんだろうと考えて音楽をつくる時に、僕は『人』のことを考えます。
それは、大学の時に周りにプロ的な音楽家が全くいなかったという事がとても大きく影響しています。
訓練を受けた音楽家だから面白い音楽が立ち上がってくるということもありますが、そうじゃない状態でいろいろな音楽が立ち上がってくるという体験もしました。
時にはすごくつまんなくなる事もある訳です。
人がどう関わっていくと音楽がつまんなくなったり、生き生きとしたりするんだろうっていうことにすごく興味がありますね。
人と関わってやっていると、そこで人が代わったり何か変化しているのを見た時に、『教育ってこういう風であったらいいんじゃないかな』を思うことはいろいろあるんです。」
池田「限りなく教育者に近いアーティストだよね。やっていることは教育だもの。」
横川「現代作曲家の人は自分の書きたいことを緻密に書いているけど、そこから先のことも考えたいということですね。そこを考えている所が野村さんたる所ですね。」
野村「全然違うんですよね、つまんなそうに演奏されるのと楽しそうに演奏されるのでは。全然違うじゃないですか。
じゃあ何でつまんなくなるんだろうとか、楽しそうになるんだろうかっていうのは、すごく気持ちが入って音を出しているのと全くやる気が無くて音を出しているのとでは、全然違うはずです。」
野村さんのインタビューは、まだまだ続きます。この後も興味深いお話が展開しますが、次号へと続きますので、どうぞお楽しみに!
第2回:特定非営利活動法人ZEROキッズ 佐々木香さん
第2回「 特定非営利活動法人ZEROキッズ 佐々木香さん」
今回のインタビューは、佐々木香さんです。
特定非営利活動法人ZEROキッズ理事長。「ZEROキッズ」は、1993年に地域の少年少女合唱団とママさんコーラスを母体として「なかのZERO大ホール」の開館記念区民参加事業、親子オペレッタをきっかけに設立されました。
2001年にNPO法人化。そうぞう力(imagination&creation)をテーマに様々な表現体験や自然体験から異年齢の子どもたちの仲間づくりを進めています。活動の集大成としてのミュージカルは、楽譜やCDとなって出版され全国で愛唱されています。
2018年10月から中野区江古田でキッズルーム「もりのいえ」の運営を受託。常設の親子の居場所として、また「音あそび」や「赤ちゃんおはなし会」等を開催し、乳幼児親子の子育て支援にも活動を広げています。
本NPOが定期的に活動している「くにポン&アッキーの音の楽校」や「おひさまリトミック」も佐々木さんからのご依頼です。
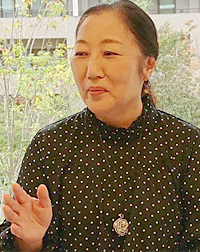
聞き手:口中常嘉(事務局長) 同席者:池田理事長・斉藤副理事長
池田さんと出会ったきっかけは何ですか?
(佐々木さん)ZEROキッズを始めてから、子どもたちに体験してもらうにはまず自分がやってみなければと思い、中野区教育委員会が主催したレクリエーションリーダー講習会に参加しました。その中に手作り楽器の講座があって国立音楽大学の繁下和雄先生が担当されていました。紙で楽器を作ったりして、これはZEROキッズの子どもたちにも体験させたいなと思い、繁下先生に講師として来ていただけないかとお願いしたら、「うちの若いの(当時の池田理事長)を紹介するよ」とおっしゃったんです。
それはいつ頃ですか?
(佐々木さん)1994年か、95年。それで池田先生の連絡先を教えてもらってお願いしたんです。
では、25年のお付き合いですね。
最初、池田さんにお会いした時の印象は?
(佐々木さん)小学校の音楽の先生で、偉ぶってないし、フレンドリーだし、面白い方という印象でした。
(池田)僕の方は、どんなことをすればいいんですか?って伺ったら、自由に音で子どもたちと遊んでくださいって。これは面白そうだと思ってその場ですぐにお引き受けしました。
(佐々木さん)ZEROキッズの活動が月2回で、学校五日制も始まったばかりの時ですね。
ZEROキッズの創立は?
(佐々木さん)1994年です。最初は、母体になった少年少女合唱団の先生にお願いしてファミリーコーラスと、幼稚園のえっちゃん先生(今は副園長)と表現遊びというのをやりました。その後、学校五日制の土曜日の休みが増えるのと合わせて、キッズの活動も月4回、毎週日曜になりました。
池田さんと「音のワークショップ」を始めて2年目に、やるんだったら単発じゃなくて続けてやろうということで「音を探そう、作ろう、遊ぼう」という連続講座にして、小学校から竹をもらって楽器を作って中学校の体育館で音楽会もしましたね。この頃からですよね、斉藤さんにもお手伝いして頂くようになったのは。
(斉藤)佐々木さんは子どもたちの表現力を育てるための様々な講座を開設して、それを定期的に開催されたり、子どもたちのミュージカルをなかのZEROホールで公演するなど、企画力とかアイデアが物凄く豊富な方なんです!
(池田)みんなで野川公園にハイキングに行って、シートを敷いた上に寝そべって、アイマスクを使って自然の音を聴いたり、糸電話で何メートルぐらい通じるかやってみたり。「オーイッ!」っていう声がどれ位遠くまで聴こえるか?というものやりました。
(斉藤)距離を測ったら「オーイ!」とか「ドラえもん!」とか言ってもあまり遠くまでは届かない。「ヤッホー!」って言うのが一番で200m位届いた。遭難した時「助けて~!」なんて言ってもあまり聞こえないことが判明。でも「ヤッホー!」じゃ誰も助けに来てくれませんよね?(笑)何でも良いから、こんなのどうかな?面白そうだよね?というのを全部やらせてもらったんです。
(池田)当時のZEROキッズは幼稚園児から中学生位まで幅広い年齢層の子どもたちが参加していて、時にはお年寄りが参加することもありました。そこで、全部、何をやってもいいよと言われていたので、子どもたちだけでなくスタッフもお年寄りもみんな一緒に音を楽しむ即興アンサンブルをやったんです。これがとても楽しかった!ああ、音を楽しむっていうのは、年齢に関係なく誰とでも一緒に活動出来るんだと、改めて実感・確認させてもらったのがこのZEROキッズだったんです。
(斉藤)こんなに自由に活動させてもらえるところは他に無いね!
(佐々木さん)池田さんと出会ったことで音楽観の転換というか、意識の転換というか、目からウロコの体験でした。ZEROキッズは表現遊びと池田さんの音遊びの二つが土台になっていると思います!音楽は誰でもできる、楽しめる。楽器が弾けなきゃいけないとか、歌が綺麗に歌えなきゃいけないとかではないという。
(口中)私も、初めて民音(民主音楽協会)で池田さんと斉藤さんの講習会をやらせてもらった時に感じました。今までのクラシックの概念というか、まず楽譜があって、楽器があって、作曲家の思いをいかに忠実に再現するかということばかり考えていたのが、全然違う。もう目からウロコ!という感じでしたね。驚きました。それから、全国、北は北海道から九州・沖縄まで、この講習会をやらせてもらいました。
(池田)その意味では、僕たちはZEROキッズの佐々木さんと民音さんに育てられました。本当にありがたいことです!
佐々木さんから見て、今後に期待することは?
(佐々木さん)今のまま楽しく自由にやっていただければそれで十分です。
(斉藤)今、ここ江古田の杜で新しく私なりの親子リトミック教室をやらせてもらっているんです。くにポン(池田)は国立音大のリトミック専攻だけど私はただ音楽に合わせて踊ったり笑ったりするのが好きなだけ。でも、お母さんと乳幼児を相手に始めさせてもらって、ここは楽しい!行けるぞ!という感じです。
(佐々木さん)最初は、赤ちゃんが対象だとどうなるのかな、という感じでしたけれど、とにかくお母さん方がみんな笑顔になってとても評判がいいんです。
(斉藤)お子さんが生後4ヶ月の時から参加されているお母さんから「ここでやるようになってから、家でも音楽を流すとそれに合わせて体を動かすようになったんですよ!」と嬉しい報告を受けました。自分の体の中から湧き出てくる動き、私のリトミックがその表現を出来るようになったきっかけになったとしたら嬉しい限りです。
(池田)大学の講義で学生に「音楽の苦手な人は?」と聞くと、必ず何人かが手を挙げます。でも“楽器の演奏や歌うこ「おひさまリトミック」(写真提供もりのいえ)とが苦手”っていうんじゃなくて、“音楽が苦手”って変だと思いませんか?実はこういった意識は学校の音楽の授業で植え付けられてしまうケースが多いんです。僕はそれを転換していきたい。
(佐々木さん)だからこそ先ほども言った、「音楽は誰でもできる、楽しめる。楽器が弾けなきゃいけないとか歌が奇麗に歌えなきゃいけないとかではない、くにポン達の“音の楽校”をやってもらっているんですよ。
(口中)日頃より私達NPOの活動に場を提供くださっていることに感謝いたします。今日はお時間を頂き有り難うございました。今後とも宜しくお願いいたします!
このインタビューの後、厚生労働省とスポーツ庁が主催する「第9回健康寿命をのばそう!アワード」が発表され、<母子保健分野>で「NPO法人ZEROキッズ」が参加98件のなかで最優秀賞を受賞されました。
中野区・江古田の杜のマンション群と地域をつなぐ多世代交流事業の成果が認められた成果です。受賞、おめでとうございます!
《関連リンク》
□ 特定非営利活動法人ZEROキッズ https://zerokids.org/
□ 江古田 もりのいえ facebook https://www.facebook.com/morinoie.egota
□ 明星大学 https://www.meisei-u.ac.jp/
□ 一般財団法人 民主音楽協会 https://www.min-on.or.jp/
第1回:阪井恵先生

第1回「阪井恵先生」
阪井恵先生は本法人の理事を務めていらっしゃいますが、現在、明星大学教育学部の教授としてご活躍されています。東京芸術大学卒業、同大学院音楽研究科修士課程、博士課程修了の学術博士です。長年、「音を聴く」や「音色」について深く研究なさってきた阪井先生に、本法人に関する事をお聞きしました。
なぜ、「音を聴く」ということに着目したのですか?
子どものころから音に関心があり、様々の音色を聴くのが好きでした。なぜ着目したかという質問にはうまく答えられないのですが、音を好む習慣が、自分の生育環境の中で培われたと思います。
文学においても様々の作家が垣間見せている音への感性やその表現に、尽きない興味を覚えます。音への関心が、音楽にアプローチする間口になっていることは、言うまでもありません。
音楽教育に携わるようなってからも、「音楽との出会いは、まず音――音色とか音の質感――が窓口になる」と無意識のうちに思っていて、それに基づく実践をしてきました。
「リズムやビートこそが音楽の窓口」というタイプの実践をなさる方もありますので、どちらがよいということではありませんし、音楽的には両者は切り離しがたいですが、自分はそういうタイプなのだなと自覚しています。
音を聴くことにより、どんなことが期待されますか?
音を聴くということは、音を発する身体活動と異なり、身体的にはむしろ静止する行為です。
教育的なことに限定して言えば、この静止的な状態で、聞こえる音に基づいた想像力を育むよう仕向けることは、他の動物にはない文化的な営みとして価値があると思います。
そのような方向付けの先に、「どこかで春がうまれてる どこかで芽の出る音がする」という古い歌の歌詞に表れているような感性が生まれます。
人間は、音として聞き取ることができないものも、脳内で画像や色や動きと結び付けて想像することができるわけです。
人による程度の差はあると思いますが、このような行為の基礎は、やはり文化的学習だと考えます。
聴覚は、動物の生存のために欠かせない精緻に進化した能力ですが、その聴覚を生存のためを越えて使えるということ自体が、すごい資質です。
個別の人間をみているとよく分からないかもしれませんが、人間全体としては、この資質が、音楽は勿論、さまざまの文化を発展させてきたのです。
音を聴くことの学習は、人を育てる大切な要素だと考えます。
音を聴くことと心の成長とは関係がありますか?
わかりません。心の成長にも色々な側面があると思うので一概にはお答えしにくいです。
「音の楽しみ方」は、他のあらゆる生活習慣などと同じで、文化的に学習できるものです。
家庭や学校でどのような経験をするか、周りの人がどのように行動しどのような発言をするか――そういうことを通じて学習すると思います。
そのような過程で身についた、音を受容する態度や、面白い音を探求しようというマインドが、ある人の場合は物事への取り組み方や考え方と関連して現れ、成長の糧になると思います。
でも、全ての人にとってそうであるとは言えないのではないでしょうか。
ただ前項でお答えしているように、人間全体としてみると、文化的発展という「大きな心の成長」につながっていることは確かだと考えます。
これまでの研究で「音を聴く(楽しむ)」ことについて、どのようなことがわかりましたか?
音は本質的にコミュニケーションに関係しています。
たとえば「あのね」という一言には、無数の言い方が考えられますが、それを言っている相手が見えず、声(音)だけをきいたとしても、相当の情報が得られます。
分析すれば、倍音成分の組み合わせなどを見ることができますが、聴覚と脳のネットワークの精緻さは、コンピュータ―をはるかに凌ぎます。
また、音は媒質(空気)の波動なので、音を聴くことは音を発している人やモノに、距離はおいているものの接触していることなのだとも言えます。
大げさなようですが、それに違いないのです。お母さんが赤ちゃんに声をかけることと触れること、これは別のことではなくてつながっていることです。
このような「音」についてのとても基本的な考察をしてみるという学習が、学校教育では欠けている、ということが分かりました。
人(児童)を対象とする研究は難しくて、科学的な数値によるデータを示して明らかにできた、と言えることは残念ながら、まだありません。
今後、音を聴くことについて、どのようなことを追究していきたいですか?
音を聴くことに、音楽科の学習の重点をもっともっとおくようにしたいです。学校の音楽授業は、「表現」と「鑑賞」という2つの領域のもとで、歌唱・器楽・創作(音楽づくり)・鑑賞の4つの活動分野を行うことになっています。
これは70年の積み上げのある考え方なので、変えるのは簡単ではないのですが、このすべての活動の基礎には「音をよく聴く」ことがなければなりません。ところがそれは自明すぎると思われていて、ほとんど話題に上らなくなっているのが現状です。
5年前から、学校の音楽授業でこれまでほとんど放置されてきた問題――いろいろな理由で音楽の授業に参加したり楽しんだりすることができていない人がいるという問題――に取り組んでいます。
2年間くらいは、個別の「困りごと」対策を考えていたのですが、その後は組織的な対策を講じない限り改善できないと悟って、「音楽授業のユニバーサルデザイン」という言葉に括られることに取り組んでいます。
「音をよく聴く」という学習は、アプローチとしては易しいことです。他の学習では困難があっても、音への素晴らしい感性をもっている人は多いのに、今の状況では認められる場がほとんどありません。
学習内容として「音を聴く」ことをもっとクローズアップすることと、「授業のユニバーサルデザイン化」をリンクさせて提案をしていきたいと思っています。
ヨイサの会を知ったきっかけは?
1998年でしたか、日本学校音楽教育実践学会という学会の大会で、斉藤明子先生(副理事長)の武蔵野第四小学校での実践を知ったことです。
とても感動したので、思わずお手紙を書きました。その時点では、お返事をいただくようなつもりはなかったのですが、すぐに折り返しご連絡をいただけてビックリでした。
そこからヨイサの会に繋がりました。ヨイサの会の先生方(ヨ:横川理事、イ:池田理事長、サ:斉藤副理事長 当時はこの3人で構成)が、驚くばかりにオープンに、私に色々教えてくださったのです。
特に、斉藤先生の授業からは、一言二言では言い表せないほど学ばせていただきました。
博士論文にヨイサの会のことを書こうと思ったのは何故ですか?
ちょうど、学習指導要領の改訂時期(2008年)に差しかかるころでしたが、この改訂は、音楽の構造(仕組み)を教え学ぶ、ということが強調される方向でした。
私はこの方向を評価しないわけではありません。しかし、構造(「仕組み」)というものを捉える視点が狭いように思い、引っかかりました。
ものすごく単純化して言うと、音楽を図面化して捉えることが音楽の理解であるかのように、展開しかねないと思ったのです。
ヨイサの会は、音楽をつくる活動は、そういう図面を引くことなのではなく、むしろ音を聴くことの学習なのだと考えていたと思います。
結果的に出来上がったものが図面に起こせないようなものでも、音を聴き合い、組み合わせを試しながら子供同士が意見を出すこと自体に価値がある、という考えに基づいていました。これは、記録しておくべき実践だと考えたのです。
この改訂で示されたような「音楽の仕組み」が分かると、音楽の楽しみ方が広がる場合もあると思います。音楽を創る上でも、先人の使っている「仕組み」を学ぶことは欠かせません。ただそれは、後付けでも学べます。
ヨイサの会の実践は、後付けで学べないものを見据えていたので、大変魅力的でした。ヨイサの先生方は、「音を聴く」実践には音楽教育としての意義はさておき、人間形成としての意義があり、それを意図していると考えておられたかもしれません。
でも私は音楽教育の基礎としての意義を、僭越ながら大変高く評価しているのです。
音楽の固有性は結局は音のチカラであって、音の響きこそが私たちの無意識の部分(要素がどうの、仕組みがどうの、と言語化できない部分)にまでも働きかけてきます。
「音へのアンテナ感度を高めること」。多様な音楽を受容して楽しむマインドのために、これ以上に大切な基礎・基本があるでしょうか。
本NPO法人にどんなことを期待していますか?
このNPO法人の活動は、広い意味での教育・啓発活動だと思っています。才能と経験とユーモアにあふれたスタッフが提供する、「しあわせな時間」は宝物だと思います。
そしてその「幸せな時間」はもって帰って、また家庭や自分の周りで実践可能でしょう。それが素晴らしいと思います
。NPOの存在が広く知られ、活動に参加する人が増えていくことを期待します。
阪井先生、お忙しい中、詳しくお話しいただきましてありがとうございます。音を聴き楽しむことは誰にでも出来る簡単なことですが、そこには大変深い意味と人間形成にとって大切な内容を含んでいるのですね。今後も研究を続けていただき、これまで以上の成果を上げていっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。




